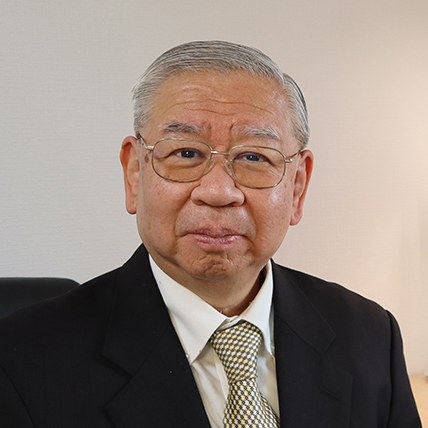はじめに
この欄では就活を含めて、大学に入学してから卒業するまでの学生生活全般におけるアドバイスを書いていきたいと思っています。学生生活で悩んだり、困ったり、迷ったりした時に、この欄を参考にしてもらえれば幸いです。
その場で懸命に励めば、そこが華である
みなさんの中には、今、学んでいる大学は第一志望の大学だったという人もいるでしょうし、第二志望、第三志望の大学だったという人もいるかもしれません。
私が大学の教員をしていた時にも、「自分はこの大学が第一志望だった」という学生もいたし、「第一志望は他の大学だった」という学生もいました。たくさん大学を受験していて、「ここは第十四志望の大学です」と言っていた学生もいました。
学生の中には、「第一志望の大学に入学できなかった」という気持ちを引きずってしまう人もいます。それは、江戸時代の末期に、若い人材が江戸に集中する中、地方にいる若者が「こんなところにいても、何もできない」と卑屈になっていたのに似ているかもしれません。
幕末の教育者、吉田松陰は、松下村塾の教育理念として「華夷の弁」(かいのべん)を掲げています。「華夷の弁」とは、「自分が生まれた土地に劣等感を持つ必要はなく、その場で励めば、そこが華である」という意味です。華というのは、ここでは「文化の中心」と理解していいでしょう。
松下村塾のある松本村(注1)という辺境の劣等感を克服して、そこにすぐれた文化的な環境を築きあげようという松陰の決意、そして、かならず松下村塾から時代に必要な人材を輩出するのだという覚悟のあらわれている言葉です。
そして、松下村塾からは明治維新において活躍した多くの人材が育っていきます。小さな私塾から伊藤博文、山縣有朋という二人の総理大臣も出て、明治期の日本の舵取りを担ってゆきます。
恵まれた環境でなくても、与えられた条件に不足があったとしても、志、願い、意欲、努力等のエネルギーを燃やし続けると、その環境の中に隠れていた可能性を見出せるようになってくる。それを考えた時に、「どこの大学に入ったかに関係なく、その場で励めば、そこが華である」ともいえるのだと思います。
実際、前述の「ここは第十四志望の大学です」と言っていた学生は、大学で懸命に励み、自分の人生の方向性を見出していきました。3年次に彼女は、「私は本当にこの大学に来てよかった。ここに来たから、自分の道が開かれた」と言っていました。現在、彼女は国際的な機関で働いています。
この欄を読んでくれているあなたが、今いる大学で懸命に励み、そこを華にすることができたら素敵だと思います。
注1:松本村:現山口県萩市椿東の一部
参考文献:古川薫(1996)『松下村塾と吉田松陰』 新日本教育図書